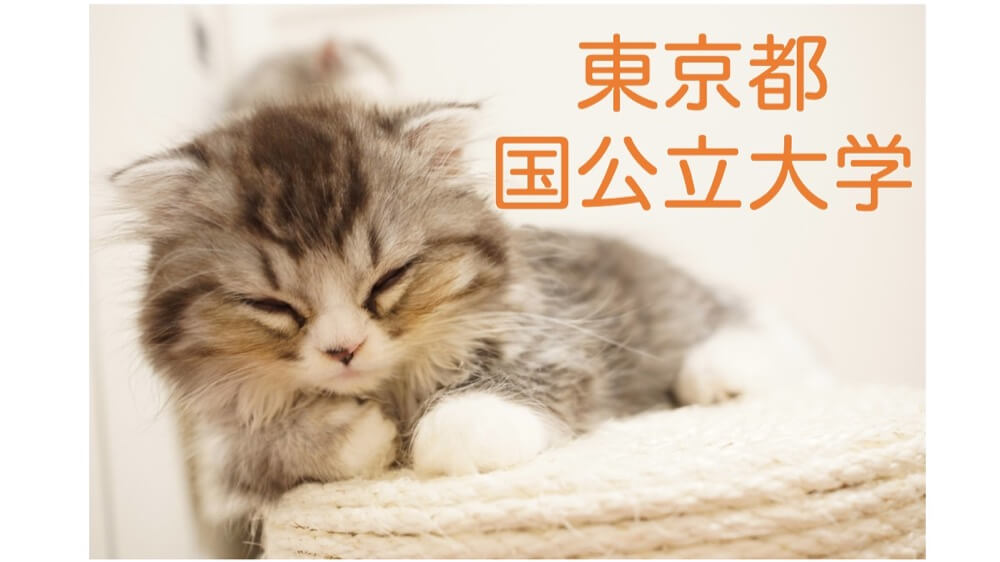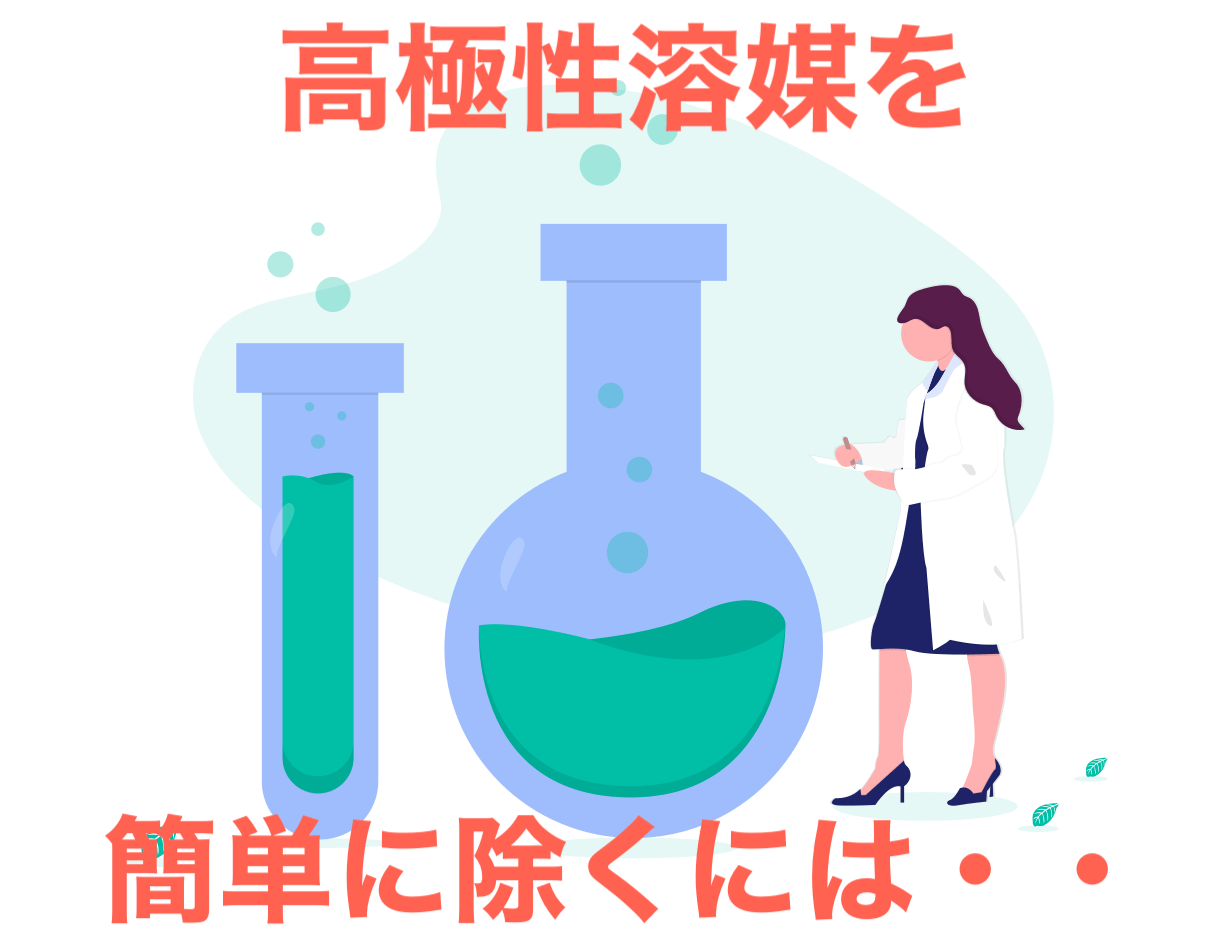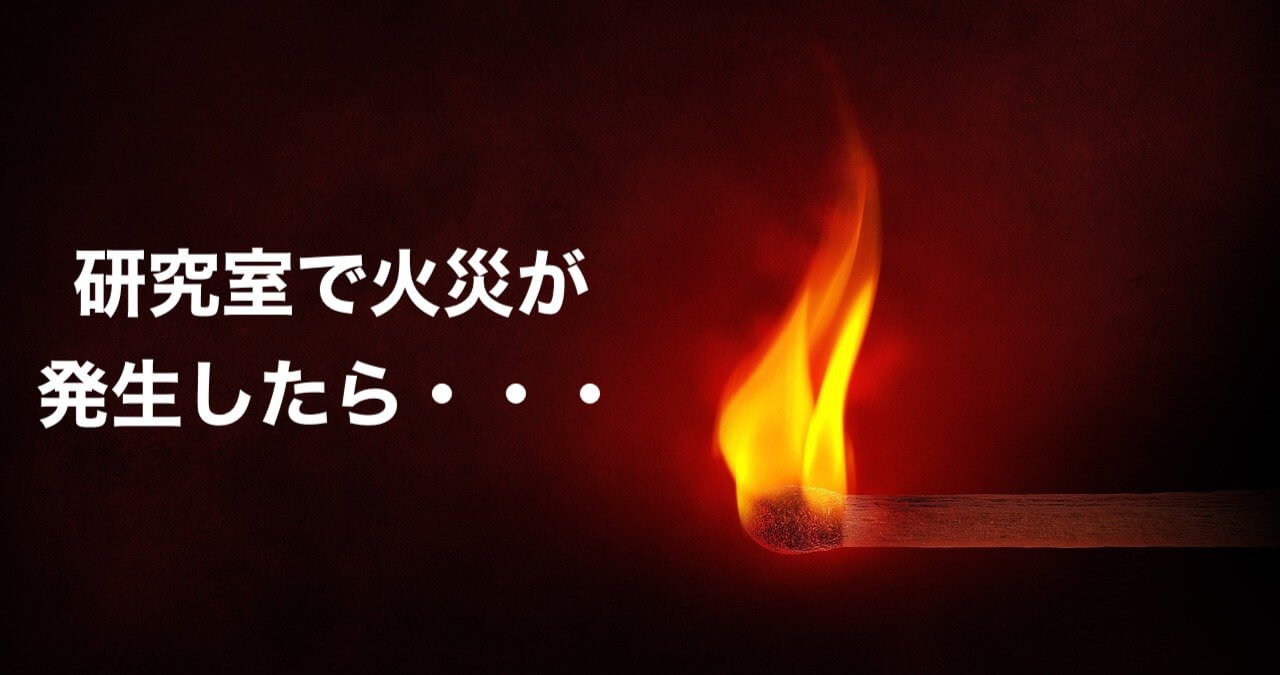
研究室で、危険なことの一つが火災です。
大なり小なり火を出した経験がある人はいると思います。かく言う私も、修士のときに小さい火を出したことがあります(^_^;)
どこでも起こる可能性のあることですが、大きな火災になると簡単には消せません。特に有機化学の研究室では油(有機溶媒)が燃えることがあるため、一般的な消火と同じではありません。
一般的な消火法と違うということは知っていても、実際、どうやって消火すればいいかまで知っている人は少ないかもしれません。
いざというときに迷わないように、ここで確認しておきましょう。
Contents
一般的な消火法
消火と聞いて最初に思い浮かべるのは「水をかける」ことだと思います。
普段の生活であれば、もちろんそれで大丈夫です。
しかし、研究室での火災では違います。「水をかけるのは間違い」くらいの認識でいたほうがいいでしょう。
消火の原理
そもそもですが、燃焼に必要なものは3つあって、①酸素の供給、②燃料の供給、③一定以上の温度です。この3つが持続することで燃焼が起こり続けます。
つまり、消火するには①〜③の1つを取り除けばいいのです。
一般的な消火で、水をかけるのは①と③を取り除くためです。水の比熱が大きいため、燃焼している物の温度が下がり、水蒸気で空気(酸素)の供給を遮断します。
しかし、有機溶媒の消火では、水をかけるのはご法度です。
というのも、消火で水をかけても有機溶媒と水は混ざらないため、温度が下がる効果は期待できません。むしろ水と有機溶媒の量によっては、天ぷら油の中の水のように突沸して油(有機溶媒)がはねる可能性もあります。
有機溶媒の消火法
それでは、有機溶媒の消火はどうすればいいでしょうか?
- A)発火原因に最適な消火器を使う
- B)消火布、消火砂をかける
- C)燃やし尽くす
最適な消火法は上の3つです。
消火器の種類

消火器は実験室(あるいは廊下)には必ず備え付けてあります。(なかったら、法律的にアウトです。)
一般的な消火器(赤)、油火災用消火器(緑)、電気火災用消火器(黄)の3つがあるので、試薬からの火災には緑の消火器を使うことが多いです。
ただし、緑の消火器も万能というわけではありません。
水にふれると危険な試薬の場合、消火器は使えません。下の表の化合物は、消火器を使ってはいけないものです。(他にもあるかもしれません。あしからず)
| 試薬 | 起こる現象 |
|---|---|
| 無機過酸化物 | 発熱・爆発 |
| 硫化リン | 可燃性・有毒なガスの発生 |
| 鉄粉・金属粉・Mg | 発火 |
| 第3類危険物(一部除く) | 発火・可燃性ガスの発生 |
| NaN3 | 自然発火性・禁水性の金属ナトリウムの生成 |
| ハロゲン間化合物 | 有毒ガスの発生 |
消火器の注意点は、使うと割と大事になるということです。大学によっては最寄りの消防署に届け出することにもなり得るので、次で紹介する消火布などで消せるときはそちらを使った方がいいでう。
消火布、消火砂
小規模な火災であれば、消火布・消火砂を使うのがベストでしょう。消火布・消火砂は酸素の供給を断つことで消火します。
消火布であれば消火できれば、片付けも楽です。安いものであれば2000円程度で購入できるので、研究室に複数枚あってもいいと思います。
私が所属したことがある研究室では備えられていることはありませんでしたが、2〜4人に1枚くらいはあってもいいと思います。
燃やし尽くす
たまに使える方法ですが、小さい火で、なおかつ燃えているものも少量であるときはそのまま燃やし尽くすのもありです。
もっとも消火布が常備されている研究室であれば、燃やし尽くすより消火布を使って消火したほうが確実です。
まとめ
以上、消火方法を簡単にまとめてみました。
消火布は消火性能、値段、片付けの楽さの3点で申し分ないです。一方、火災の規模が大きい場合は消火器が必要です。適切に使い分けましょう。
一番いいのは火災が出ないことですけどね。