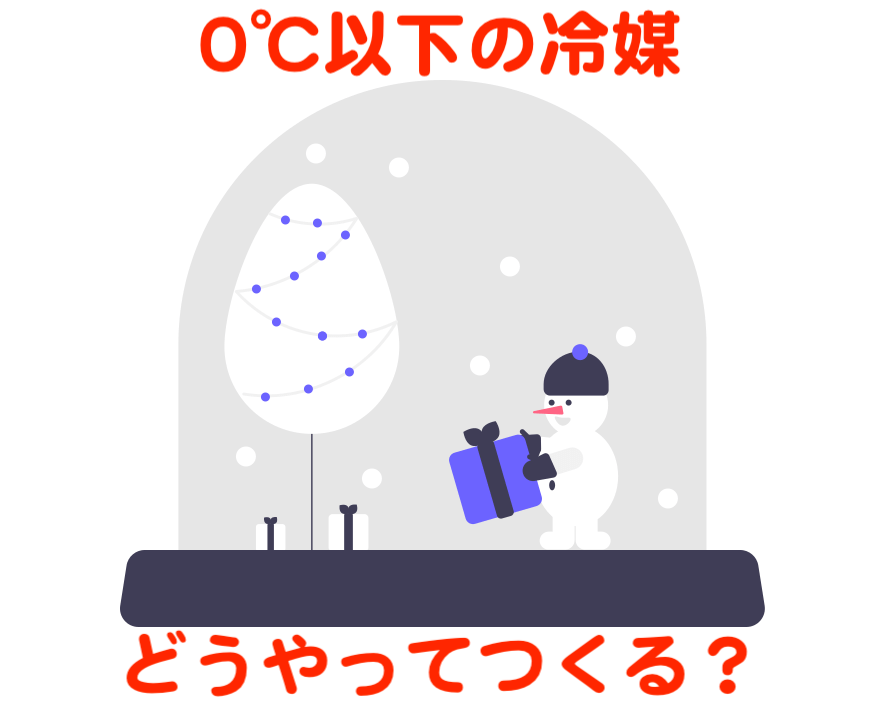
- 氷点下以下の温度を溶媒とドライアイスor液体窒素で作る
(冷却装置があればそれが一番)
最近は冷却装置が普及してきて、多くの研究室で持っていますが、教授の方針であったり、ほとんど使わなかったりなどの理由で、研究室にないこともありますね。
そういうときには自分で一定の温度の冷媒を作る必要がありますが、冷媒の温度は教員でも知らない人もいます。
ごくたまにですが、就活の面接のときに面接官から質問されたという話も聞いたこともあります。
使う機会は少ないかもしれませんが、知識として覚えておくといいと思います。もしくは、このページに書いてあったな、ということだけでも覚えておいてください。
Contents
冷媒の温度
冷媒の温度を表にまとめました。
氷-塩で温度に幅があるのは、塩の量で温度が変わるからです。温度を下げたいときは塩の量を増やします。
| 冷媒 | 温度(℃) |
|---|---|
| 氷 | 0 |
| 氷-メタノール | -10 |
| 氷-塩 | -5〜-20 |
| エチレングリコール-ドライアイス | -11 |
| 3-ヘプタノン-ドライアイス | -38 |
| アセトニトリル-ドライアイス | -41 |
| クロロホルム-ドライアイス | -61 |
| エタノール-ドライアイス | -72 |
| アセトン-ドライアイス | -78 |
| 酢酸エチル-液体窒素 | -84 |
| メタノール-液体窒素 | -98 |
| エタノール-液体窒素 | -116 |
| ペンタン-液体窒素 | -131 |
(引用:若手研究者のための有機合成ラボガイド)
注意点
溶媒を完全に凝固させない
上記の温度の多くは、それぞれの溶媒の凝固点です。
当たり前ですが、冷やしすぎると凝固します。
しかし、冷媒が凝固しているとフラスコをきちんと冷却できません。そのため、冷媒の入れすぎに注意しましょう。
理想は凝固した溶媒が少し浮いているような状態です。氷が水に浮いている状態を想像してもらえればわかりやすいと思います。
冷却剤の種類
冷却材はドライアイスと液体窒素の2種類です。
ドライアイスの昇華点が-78℃なので、その温度まではドライアイスで冷やせます。-78℃以上のときに液体窒素を使って冷やしても問題はないです。
ドライアイスがないからといって、わざわざ買ったりせずに、液体窒素で代用しましょう。
温度計を壊さないようにする
また、冷媒の温度を測るときに注意すべきこともあります。
液体窒素を冷媒に入れると、最初に煙(窒素)が出て、何秒か経つと煙が落ち着きます。そうなったときに冷媒に液体窒素が浮いている状態になります。(水に油が浮いているような状態)
温度計が直接、液体窒素に触れると急激に温度が下がりすぎてしまい、温度計のアルコールが切れることがあります。
修復不可能に壊れるわけではないですが、面倒なので注意しましょう。
あと、温度計で冷媒と液体窒素をかき混ぜると、温度計を器にぶつけて割ることもあります。
こっちは修復不可能なので、温度計でかき混ぜるのはやめたほうがいいです。
まとめ
いろいろな温度の冷媒の作り方はまとめました。
実際に使うのは、-40℃でアセトニトリル-ドライアイス、-78or-80℃でアセトン-ドライアイス、-100℃でメタノール-ドライアイスの組み合わせが多いです。
冷媒作りの注意点もまとめたので、作ってみるときは注意してみてください。










